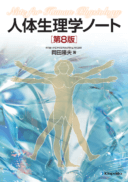人体の解剖生理学
第3版
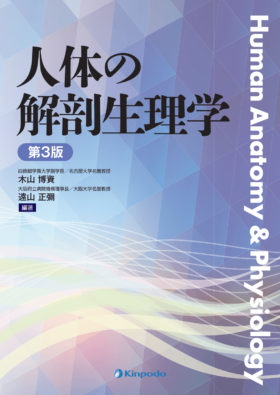
医療関連領域の学生が人体の構造(解剖学)と機能(生理学)の膨大な知識を理解できるよう簡潔にまとめた1冊
内容紹介
近年、医学の分野ではがん免疫療法や遺伝子治療などの画期的な進展が見られます。しかし一方で、精神疾患や機能性身体症候群のように、原因が十分に解明されていない疾患も依然として多く存在します。こうした疾患の治療を目指すには、解剖学や生理学といった基礎医学の理解が不可欠です。これらの学問は、正常な身体の構造や機能を明らかにするものであり、現在も進化を続けています。
また、解剖学や生理学は生化学や薬理学などの他の基礎医学分野と密接に関わっており、決して独立した学問ではありません。そのため、これらを学ぶ際には関連分野とのつながりを意識することが大切です。そして、医学は常に進歩し続ける分野であるため、新しい知識を積極的に学び、変化に適応する姿勢が求められます。
本書では、基礎知識を確実に身につけられるよう、内容を整理し、可能な限り最新の知見を取り入れて改訂しました。本書を通じて、医学が日々発展する学問であることを実感し、その魅力を感じていただければ幸いです。
序文
この度、「人体の解剖生理学」第3版を出版することができました。第3版まで版を重ねることができたのは、ひとえに本書を使って講義をされている先生方のご支援の賜物であります。私は37年にわたり4つの大学の医学部医学科で解剖学を担当し講義実習をやってまいりましたが、本年よりリハビリと看護の医療系大学で教育にあたっております。焦点を学問のより本質にあてること、さらにその本質の背景を少しでも説明することの大切さを感じております。膨大な基礎医学や臨床医学の知識を勉強し看護師や理学療法士などの国家資格を有して実際に患者さんに接していくには、今までに積み上げられたあまりにも多くの知識の集大成を学ばなければなりません。一方で、医学の世界では日々新たな発見が報告されており、その知識は現在も急速に膨張し続けています。
現在、華やかながん免疫療法や遺伝子治療など医学は日々高速で進化しています。しかし、精神疾患あるいは機能性身体症候群などのように原因が不明の疾患はまだまだたくさんあります。それらの疾患の治療を目指す最先端医学の根底には、正常形態を明らかにする解剖学と、正常構造に裏打ちされた機能を明らかにする生理学があります。とはいうものの、基盤となる解剖学や生理学は未だ完成したものではなく、今も日々進化しています。例えば脳脊髄液がどのようにクモ膜下から頭蓋腔外に流出するかなどは最近になってその構造が明らかになり、あるいは脳内の免疫細胞であるミクログリアの起源やその性質がはっきりし始めたのもここ10年以内の出来事です。このように学問は日々進化し続けていることを踏まえてこの教科書を利用していただけると幸甚です。また、解剖学・生理学は生化学や薬理学など様々な基礎医学領域と互いに関連しあっており、決して独立して存在するわけではありません。解剖生理を学ばれるにあたっては、どうぞ周辺分野の科目との関連を常に意識して勉強してください。例えば最近話題のGLP-1作動薬のような糖尿病や肥満の新しいお薬が出た時に、GLP-1はどこから分泌され、どこに受容体が存在するのか、どのように働くのか。ここで学んだ基本的な解剖学と生理学の知識に、自ら新しい知識を追加していかなければなりません。皆さんは医療従事者として常に新たな知識をアップグレードし続けていくことになります。
このような状況を踏まえて、執筆者の先生方には、基本的な知識がしっかりと身につくようにわかりやすく書いていただくとともに、なるべく最新の知見も組み込んで加筆していただき第3版が完成しました。
最後に本書の発刊にあたり、多大なご尽力をいただいた執筆者諸氏、発刊のためにひとかたならぬ労をお取りいただいた金芳堂編集部の一堂芳恵さんに深甚の感謝の意を表します。
令和6年12月
四條畷学園大学副学長
名古屋大学名誉教授
大阪市立大学名誉教授
木山博資
目次
1章 人体の構成
1 概要
2 人体を構成する主な分子
3 細胞
4 組織
5 器官と器官系
6 人体を被う皮膚
7 器官・組織を包む膜
8 人体の区分
9 内部環境の恒常性
2章 声帯の防御機構(血液と免疫系)
1 非特異的生体防御機構(自然免疫)
2 特異的生体防御(獲得免疫)
3 生体防御系の発生・発達
4 血液の成分と機能
5 止血機構
6 血液型
3章 循環系
1 心臓血管系
2 リンパ系
3 循環器系の発達・老化
4章 神経性調節(神経系)
1 神経系のしくみ
2 神経組織
3 中枢神経系
4 末梢神経系
5 視覚
6 聴覚と平衡覚
7 嗅覚と味覚
8 皮膚感覚
5章 液性調節(内分泌系)
1 ホルモンの作用機序
2 ホルモン分泌の調整
3 内分泌器官の構造と機能
6章 運動器系(筋骨系)
1 骨
2 関節
3 筋
4 人体の骨格
7章 呼吸の機構
1 換気
2 ガス交換
3 ガスの運搬
4 呼吸調節
8章 栄養摂取の機構
1 消化器系の概観
2 口腔の構造と機能
3 咽頭と食道の構造と機能
4 胃の構造と機能
5 膵臓の構造と機能
6 肝臓と胆嚢の構造と機能
7 小腸の構造と機能
8 大腸の構造と機能
9 消化の相
9章 排泄の機構(泌尿器系)
1 腎臓の構造と機能
2 尿の生成
3 上部尿路と下部尿路
4 蓄尿と排尿、および陰茎
10章 性と生殖に関する機構
1 男性の生殖器
2 女性の生殖器
執筆者一覧
■編著
木山博資 四條畷学園大学副学長/名古屋大学名誉教授/大阪市立大学名誉教授
遠山正彌 地方独立行政法人大阪府立病院機構理事長/大阪大学名誉教授
■執筆者一覧
澤井元 大阪公立大学名誉教授
板東良雄 秋田大学大学院医学系研究科形態解析学・器官構造学講座教授
河合良訓 Adati Institute for Brain Study(AIBS)
岩田幸一 日本大学歯学部生理学講座特任教授
戴毅 兵庫医科大学医学部解剖学神経科学部門主任教授
李佐知子 名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学准教授
福田敦夫 医療法人社団木野記念会福田西病院学術顧問/浜松医科大学特命研究教授・名誉教授
松本-宮井和政 大阪公立大学大学院リハビリテーション学研究科教授
河谷正仁 秋田大学名誉教授
大島千佳 福井県立大学大学院健康生活科学研究科教授