誤嚥性肺炎 70の疑問に答えます
第2版
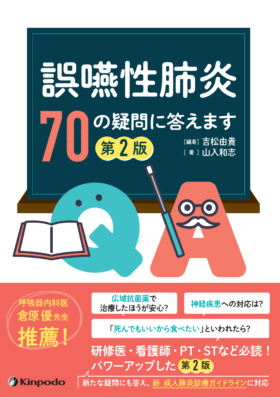
| 編著 | 吉松由貴 |
|---|---|
| ガイズ病院/セントトーマス病院老年科、グリニッジ大学人間科学科 | |
| 著 | 山入和志 |
| 大阪市立総合医療センター呼吸器内科 |
- 【 冊子在庫 】

電子書籍書店で購入
2024年4月に7年ぶりに改訂された「成人肺炎診療ガイドライン」を踏まえた内容に更新!
内容紹介
旧版の出版から、3年弱が経ちました。超高齢社会の中、誤嚥性肺炎患者は今後も増えると言われています。そのため、誤嚥性肺炎に携わる医師・医療者は、呼吸器内科に限らず、他の診療科でも診るコモンな疾患です。2024年改訂の「成人肺炎診療ガイドライン」では、誤嚥性肺炎の項目が加わりました。また、その項目の執筆に著者のひとり、吉松先生も参加しています。本書は、誤嚥性肺炎に対して、臨床現場で出てくる様々な問題や疑問に対して、解決方法などを提示しています。誤嚥性肺炎患者がますます増える中、旧版で伝えきれなかった医師・医療者の疑問をまとめ直しました。
序文
推薦のことば
日本の高齢化率は約30%です。中には、40%を超えている地域もあるでしょう。近くに暮らす人の半数近くが高齢者ともなれば、「誤嚥性肺炎」はもはや地域社会で抱える問題として避けられません。どの疾患で診療していても、高齢者の患者さんが多いですから、今後「誤嚥性肺炎パンデミック」の時代は間違いなく到来します。
さて、この本、第2版になります。それほど誤嚥性肺炎に注目が集まっていることの証ですが、専門知識に裏打ちされた筆者らの熱意があってこそ実現できたハイクオリティの書です。「患者さんに寄り添う」という言葉が、ただのスローガンではなく具体的な行動に昇華されている様子が、随所に描かれています。
誤嚥性肺炎は、医療チーム全体の力が問われる疾患です。診断や治療だけでなく、患者さんの退院後の生活やその人らしい生き方を見つめる場面が多くあります。それは文章で伝えられるほど、簡単なものではありません。一人ひとりの患者さんには、一つ一つの物語がある。私たち医療者は悩みます。絶食を続けるべきか、少しでも食事を取らせるべきか。安全と希望のはざま。葛藤する日々。
この本は、「嚥下おでこ体操」などの具体的な訓練方法から、「とろみを嫌がられるとき」の対応まで、日常診療での細かな工夫が詳述されていることが特徴です。また、「むせない誤嚥」の評価方法など実践的な視点も解説されています。また、食事場面の観察ポイントをまとめた表や、誤嚥性肺炎の原因チェックリストなど、明日からすぐに活用できるツールがちりばめられています。
私にとって、誤嚥性肺炎とは、どちらかといえば医療者が苦しい思いをして対峙する疾患だと思っていました。しかし、著者の二人は決して悩み苦しみ抜く疾患として捉えておらず、患者さんに何ができるだろうかという突破口を見つけることをまるで楽しみにしているかのような、前向きな姿勢です。たぶんそれは、「何を以て誤嚥性肺炎の治療と成すか」について、見えている景色が私たちと少し違うからかもしれません。
筆者らは、医療のゴールを「治すこと」だけではなく、「その人がどう生きたいか」に目を向けています。「誤嚥性肺炎だからこうする」という既成概念にとらわれず、「その患者さんにとって誤嚥性肺炎をどう考えるか」です。患者さんにとっての最善は、いつもガイドラインの中にあるとは限りません。そんな視点で診療を進めたい方に、ぜひおすすめしたい一冊です。
2025年2月
倉原優
はじめに(改訂に際して)
誤嚥性肺炎の診療は、単調なようで、奥深い世界です。鑑別診断や抗菌薬治療はもちろん、栄養面への介入、体調の変化への対応、他職種との協力体制、家族背景や退院後の生活への配慮、緩和ケアや終末期医療……。医師として長く臨床をしていく上で、大切なことがたくさん詰まっています。これほどの全人医療を教わる機会はなかなかありません。若手の頃に患者さんに向き合って真摯に診療することで、専門分野に進んでからも必ず役に立つものです。
私たちは卒後まだ何もわからないときから、淀川キリスト教病院の呼吸器内科で、育てていただきました。誤嚥性肺炎の患者さんを主治医として受け持ち、熱意溢れる多職種の方々による全人医療を目の当たりにしました。この初めの5年間で教わったことを基盤に、嚥下やリハビリの診療を学んできた吉松と、感染症領域で修練を積んだ山入が力を合わせ、2021年に一冊の本となりました。
そして本書の公開後、予想を超える方々がお手に取ってくださり、診療場面で活用いただいている様子や、新たな疑問をお寄せくださいました。またこの間に、誤嚥性肺炎に関するエビデンスが急増するとともに、「成人肺炎診療ガイドライン2024」や「在宅における末期認知症の肺炎の診療と緩和ケアの指針」が公開され、筆者もこれらに携わってきました。そこで今回、新たな疑問を追加する形で、大きく改訂する運びとなりました。皆さま方のお声で本書がこうして改訂を遂げ、筆者冥利に尽きる思いです。誤嚥性肺炎の診療で抱く疑問を、少しでも解決へ導く道しるべとなることを願っております。
2025年2月
吉松由貴、山入和志
目次
第1章 誤嚥性肺炎かなと思ったら(外来編)
Q1 そもそも誤嚥性肺炎って?
Q2 誤嚥性肺炎と誤嚥性肺臓炎の区別は?
Q3 胸部CTは必要?
Q4 鑑別疾患は?
Q5 外来での原因精査は必要?
Q6 グラム染色は必要?
Q7 血液培養は必要?
Q8 迅速検査は必要?
Q9 入院適応は?
Q10 外来ではどのような面談が必要?
Q11 外来治療の際の抗菌薬選択のポイントは?
Q12 外来治療でできる指導やサポートは?
第2章 入院で受け持つことになったら(病棟編1)
Q13 病歴聴取や身体診察で、気を付けることは?
Q14 誤嚥の原因の調べ方は?
Q15 神経疾患の対応は?
Q16 消化器疾患の対応は?
Q17 呼吸器疾患の対応は?
Q18 サルコペニアの対応は?
Q19 薬剤性の誤嚥の対応は?
Q20 入院治療の際の抗菌薬選択のポイントは?
Q21 はじめの指示の出し方は?
Q22 はじめは絶食?
Q23 薬だけ続けていい?
Q24 口腔ケアのコツは?
Q25 吸引の目安や、排痰のコツは?
Q26 呼吸リハビリテーションは、いつ行う?
Q27 不穏時の鎮静や抑制は、やむを得ない?
Q28 STの介入は、いつ依頼する?
Q29 食上げはいつ、どのようにする?
Q30 むせない誤嚥は、どうみつける?
Q31 嚥下内視鏡や嚥下造影はいつ行う?
Q32 胃管やCVはいつ使う?
Q33 気管切開があっても食べられる?
Q34 算定できる加算は?
第3章 入院の診療がうまくいかないとき(病棟編2)
Q35 1食べてくれないとき、どうする?
Q36 とろみを嫌がられるとき、どうする?
Q37 培養での検出菌の評価は?
Q38 治療効果判定はいつ、どのようにする?
Q39 熱が再燃したら、広域抗菌薬に変更する?
Q40 また誤嚥してしまったので、絶食?
Q41 誤嚥性肺炎を予防する薬は?
Q42 胃瘻やCVポート、誤嚥防止術の適応は?
Q43 酸素が切れないとき、どうしたらよいでしょうか
Q44 職種間のズレは、どうすればよい?
Q45 入院中の面談で気を付けることは?
第4章 退院に向けて(退院支援・地域連携編)
Q46 退院か、転院か?
Q47 転院が不安といわれたら?
Q48 診療情報提供書の書き方は?
Q49 退院時の食事指導は?
Q50 受診の目安や、地域との連携は?
Q51 誤嚥しやすい患者さんを外来でみるには?
Q52 家でもできる評価や訓練は?
Q53 肺炎球菌ワクチンの効果は?
Q54 ウイルスワクチンはいつ誰に投与する?
第5章 どうしてもくならないとき(緩和ケア編)
Q55 嚥下機能がよくなるかどうかの見極めは?
Q56 ご家族に納得してもらうには?
Q57 「死んでもいいから食べたい」といわれたら?
Q58 生命予後の予測方法は?
Q59 痰絡みなど、つらい症状を緩和するには?
Q60 ご家族のケアは?
第6章 もっと学びたいと思ったら(番外編)
Q61 誤嚥性肺炎の診療に必須の要素は?
Q62 誤嚥性肺炎の診療について教育する方法は?
Q63 多職種連携のコツは?
Q64 誤嚥性肺炎の診療で、プロカルシトニンは使用しますか?
Q65 誤嚥性肺炎における抗菌薬の適正使用とは?
Q66 外来でサッと嚥下評価を行うには?
Q67 栄養剤を美味しく飲んでもらうには?
Q68 「ビールを飲みたい」といわれたら?
Q69 肺炎を繰り返す患者さん、海外ではどうしている?
Q70 肺炎を「治療しない選択肢」とは?
ひとやすみ
食事指導を守れず誤嚥したと思ったら……
急な体調の変化も地域で診ていくための英国の体制
大人しい患者さんだなと思っていたら……
J-Oslerと誤嚥性肺炎
地域へバトンをつなぐ、退院前ST訪問
主治医からみた、誤嚥性肺炎
誤嚥性肺炎から学ぶ緩和ケア
呼吸器内科に進んだ道
ガイドライン改訂を経験して
索引
著者プロフィール





