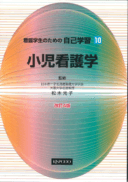生物と生命倫理の基本ノート
-「いのち」への問いかけ- 第4版

「人間とは何か」「いのちとは何か」
内容紹介
本書は、「人間とは何か」「いのちとは何か」といった根源的な問いを考え、追求する生物学と生命倫理の入門書です。
前半(第1~6章)では、生物学の基本的な知識を学び、生き物の機能やシステムを分子レベルで解説。後半(第7章以降)では、それを基に生命倫理のさまざまな課題を取り上げ、医療技術の目的や応用を倫理的に考察しながら、「科学・技術」と「いのち」との関わりについて述べています。
全章で質問形式を採用し、Discussion(討論課題)を設けることで、読者が自ら考え、議論を通じて他者の意見を尊重しながら理解を深められる構成となっています。本書を通じて、いのちの不思議さに畏敬の念を抱きつつ、科学や医療に向き合うヒントを得てほしいという願いが込められています。
序文
序 ― 第4版の発刊に際して
2020年のノーベル化学賞に、「ゲノム編集」の画期的な技術を開発した二人の科学者が選出されました。「ゲノム編集」とは生き物が持つ全遺伝情報(ゲノム)を自在に書き換える(編集)技術のことです。この手法を医療に応用すれば、病気の遺伝子を編集し根本的に治療することができます。その恩恵は計り知れません。しかしその一方で、人間の改変や選別が遺伝子レベルで行われる可能性も出てきます。
科学技術をどのように使うのかという問題は、生命科学の発展とともに常に問われてきました。しかし、近年の技術はその存在自体がある種の「頑な傾向」を帯びていることは否定できず、それによって重要な鍵となる規範や価値観もどこか行き詰まりが来ているような気もします。
不可能を可能にする技術が目の前に横たわり、多くの人が当然のように利用するようになると、社会の「あたりまえ」の範囲が拡大し、「なぜ」と疑問を持つことがなくなります。生まれる前に余分な遺伝子を除き、生きている間に変異があれば発症する前に取り除くという遺伝子の操作によって、病気や「障害」がないことがベストな生き方となり、それ以外の人生を考えることもなくなります。このような考え方は、「終末期」の医療のあり方にも影響します。病気や「障害」がある生き方を許してこなかったからです。寝たきりになり社会に貢献できない自分を惨めな存在だと自分自身も思うと、延命治療も「無駄」となります。社会もそれを良しとすると、「それでも生きたい」という選択肢はなくなります。多くの局面で「自己決定」が強調されていますが、結局1つの答えのみを選択せざるを得ない社会を私たち自身がつくっているといえます。
技術があまりにも便利で夢が叶うものであればあるほど、どこに問題が隠れているのか、何が切り捨てられていくのかを想像することもなく結論を見出してしまいがちです。改めて、ミクロの世界で積み上げてきた科学技術の実績とともに、社会の中で他の生き物と共生しながら「多様に生きていく」人間を総合的に捉えつつ、いのちとは何かについて考えていくことが重要になってきます。
いのちはどこから来て、どのような仕組みで歩み続け、そしてどこへいくのでしょうか。見えるようで見えない得体の知れないものがいのちかもしれません。しかし、今ここにいる「私」は、45億年の間、必然と偶然を積み重ねあらゆる環境を潜り抜けてきた歴史の産物であることは確かです。今ここに生きているということ自体が実に稀な賜物としか言いようがありません。しかも、それぞれが異なり、かけがえのない唯一のいのちです。このことに誇りと責任を持ち、自分の命を大事にし、誰もが誰にも邪魔されず自分らしく生きていくことが大事です。自己決定もこの意味で重要です。
ただ、独りだけでは生きていけません。実際、独りでは生きていないし、生きていく必要もありません。互いに支えてこその人であり、人と人の「間」を上手に保つことこそ人間です。この「人」の「間」に多くの網を作ればたくさんの人たちと支え合うことができ、持ちつ持たれつのいのちとなります。他者の力を、網を通じて自由に貸し借りできるのが人間です。貸し借りの前提には、認め合い許し合える関係性が不可欠です。今、「自己決定」がすべての議論を断ち切るような形で台頭しているならば、こんな関係性が不在のままだからかもしれません。
常に問われるのは「いのちがここに在る」とはどういうことかという根本的な問題です。もちろん、いのちの問いに普遍的な答えはありません。答えがないからこそ、問い続けなくてはなりません。そのなかで少しでも納得いく方向を見出すことが生命倫理の真髄だと思います。
今回の改訂にあたって、冒頭にも記述したように「ゲノム編集」という項目を加筆しました。それを含む1~6章までは生物学に関する基礎的な知識を中心に、生きものが持つ機能やシステムを分子レベルで解説しています。それを基礎に、7章からは様々な生命倫理の課題を取り上げています。医療技術の目的や応用を倫理的に考察し、「科学や技術」と「いのち」の関わりを考えていきます。
本書は、大学や専門学校の半期の講義に対応できるように14章構成としました。全章を通してDiscussionを取り入れています。グループやクラスで議論し、自分の思いや考えを語り、同時に他の人の意見を尊重し耳を傾けてください。本書を通じ、いのちの持つ不思議さに畏敬の念を感じながら、科学や技術や医療に向き合っていくヒントにしていただけたら幸いです。
最後になりましたが、出版の機会を与えてくださり、ご指導いただいた東洋英和女学院大学名誉教授の大林雅之先生に厚くお礼申し上げます。また、新たな社会の動向に合わせ、何度も文章に目を通していただき適切なご助言をくださった金芳堂編集部の一堂芳恵様、そして、私の無理難題な依頼に応じて、的確なイラストを描いてくださった河合敬一先生に、心から感謝の意を申し上げます。また、一緒に勉強してきた多くの医療専門職の学生さんに、心からお礼申し上げます。
2025年2月
西沢いづみ
目次
1章 あなたにとって「いのち」とは
1.いのちを問う
2.いのちを考える
3.いのちを想像する
2章 ヒトも生きものの一員である
1.ヒトはどこからきたのだろう―生命の始まりとその歴史
- 1-1 無機物から有機物へ
- 1-2 細胞の出現
- 1-3 陸にあがった生物たち
- 1-4 哺乳類の出現
- 1-5 ヒトの誕生
2.生きものの「共通性」と「多様性」と「共生」
- 2-1 共通性
- 2-2 多様性
- 2-3 共生
3.生きるという字
4.まとめ
Discussion
3章 生命をつくりだす場「細胞」と遺伝情報「DNA」
1.細胞の構造
2.細胞の機能
3.核の中のDNA
- 3-1 二重らせん構造と遺伝情報の保存
- 3-2 DNA・遺伝子・染色体・ゲノムの関係
4.DNAのはたらき
- 4-1 自己複製
- 4-2 タンパク質合成
5.遺伝と遺伝情報の伝え方―細胞分裂
- 5-1 体細胞と生殖細胞
- 5-2 体細胞分裂
- 5-3 減数分裂
- 5-4 減数分裂による多様性のしくみ
- 5-5 「分化」はメチル化のおかげ
4章 遺伝子を探る、知る 遺伝子研究の発展―ヒトゲノム解析へ
1.DNAの発見からバイオテクノロジーへ
2.バイオテクノロジーの発展
- 2-1 遺伝子組み換え技術
- 2-2 アシロマ会議
- 2-3 DNAの塩基配列決定技術
3.ヒトゲノム解析計画
- 3-1 倫理的・法的・社会的課題の検討グループ
- 3-2 全ゲノムの解読完了による結果
4.遺伝子研究と医療
- 4-1 遺伝子診断
- 4-2 遺伝子診断の倫理的課題
- 4-3 遺伝子治療
- 4-4 遺伝子治療の倫理的問題
- 4-5 オーダーメイド医療(tailor made medicine)
5.全ゲノム解析がもたらすもの
- 5-1 遺伝子情報の管理
- 5-2 遺伝子決定論
補足資料
Discussion
5章 遺伝子を操作する―ヒトゲノム編集で命を作り出す
1.クリスパー・キャス9
- 1-1 探して、切る
- 1-2 DNAの修復
2.ゲノム編集による遺伝子治療
3.ヒト受精卵・生殖細胞に対するゲノム編集の規制
- 3-1 受精卵のゲノム編集の緩和
- 3-2 ゲノム編集されたベビーの誕生
4.遺伝子レベルの優生学
5.ゲノム編集の問題点―優生思想の助長
Discussion
補足資料
コラム 再生医療―ES細胞・iPS細胞
6章 遺伝性疾患の話
1.形質と遺伝
2.遺伝子の変異
3.遺伝性疾患
- 3-1 単一遺伝子疾患
- 3-2 染色体異常疾患
- 3-3 多因子疾患
- 3-4 遺伝子多型(DNA多型)とSNP(スニップ)
補足資料
7章 生命倫理の歴史と課題―いのちを守るための原則
1.米国生まれのバイオエシックス
2.バイオエシックスの最初の議論
3.医療におけるパターナリズム
4.人体実験
5.被験者の自発的同意とインフォームド・コンセント
6.患者の権利運動
7.日本におけるインフォームド・コンセントの普及
8.医療技術の変化に伴う倫理問題
9.生命の尊厳(SOL:sanctity of life)
10.生命の質(QOL:quality of life)
11.パーソン論
12.人間の尊厳(Human Dignity)
13.優生学と優生思想
14.自己と自己決定と自己決定権
- 14-1 自己決定は万能か
15.告知
補足資料
Discussion
8章 医療資源の配分─誰が生き、誰が死ぬのか
1.医療資源の配分と問題点
2.腎臓透析療法の現状
3.透析器の開発と患者選抜問題
- 3-1 「誰が生き、誰が死ぬのか」の選抜
- 3-2 「誰が生き、誰が死ぬのか」の基準
4.医療資源配分問題をどのように考えるか
5.パンデミックがもたらした医療資源の配分
- 5-1 新型コロナウイルス感染症拡大
- 5-2 COVID-19における「トリアージ」問題
- 5-3 イタリアの医療体制
- 5-4 「COVID-19の感染爆発時における人工呼吸器の配分を判断する
プロセスについての提言」
- 5-5 集中治療を譲る意志カード
- 5-6 日本の医療体制
補足資料
Discussion
9章 生殖補助医療─子は授かるものから、つくるものへ─
1.「不妊」と「不妊症」
2.生殖補助医療(ART)
- 2-1 人工授精
- 2-2 体外受精と顕微授精
- 2-3 代理懐胎(代理出産)
3.生殖補助医療がもたらす問題
- 3-1 治療による強い副作用と低い妊娠率
- 3-2 多胎妊娠と減数手術
- 3-3 凍結精子・凍結卵子・凍結余剰胚
- 3-4 余剰胚の研究利用
- 3-5 親子関係に及ぼす影響
- 3-6 子どもの出自を知る権利と匿名
4.代理懐胎の状況と問題
5.生殖補助医療に関する日本の規定と課題
- 5-1 生殖補助医療特例法の内容と課題
- 5-2 親子関係・出自を知る権利の不問
6.より強くなる出産への願望
補足資料
Discussion
10章 胎児を探る、受精卵を探る─子はつくるものから、つくられるものへ─
1.出生前診断
- 1-1 出生前診断の種類
2.受精卵診断(着床前診断)
3.出生前診断と受精卵診断に付随する問題
- 3-1 出生前診断と選択的中絶
- 3-2 受精卵診断と受精卵の破棄
4.出生前診断・受精卵診断導入の歴史的経緯
- 4-1 優生思想の展開
- 4-2 日本における優生政策の展開―国民優生法
- 4-3 優生保護法
5.国民の資質向上に向けて(1960~1970年代)
- 5-1 不幸な子どもの生まれない運動
- 5-2 障害者運動と女性運動の動き
- 5-3 内なる優生思想
6.らい予防法
7.母体血清マーカー検査をめぐる論争
8.母体保護法(1996年~)
9.新型出生前検査(NIPT=無侵襲的出生前遺伝学的検査)
- 9-1 NIPTをめぐる指針
- 9-2 NIPTの対象拡大の指針
- 9-3 出生前検査認証制度専門委員会報告書による転換
- 9-4 検査実施施設の拡大と問題点
10.人工妊娠中絶をめぐる各国の議論
11.完璧な赤ちゃんを産む
補足資料
参考 不妊治療および人工妊娠中絶に関する法的位置づけとその歴史
Discussion
11章「こうのとりのゆりかご」と養子縁組
1.「こうのとりのゆりかご」設置
2.預けられた赤ちゃんの行方
3.「ゆりかご」の14年間
- 3-1 預け入れ件数
- 3-2 出産場所
- 3-3 預け入れに来た者
- 3-4 身元の判明
- 3-5 養育状況
- 3-6 預けた理由
- 3-7 相談窓口への相談件数
4.「ゆりかご」を生み出した社会的背景
- 4-1 妊娠・出産・子育ての支援体制
- 4-2 戸籍の問題・パートナーの自覚の問題
- 4-3 養育拒否と虐待
5.匿名のシステムと子どもの出自を知る権利
- 5-1 内密出産
6.特別養子縁組制度
- 6-1 特別養子縁組制度の特徴
- 6-2 児童福祉法の改正
- 6-3 特別養子縁組あっせん法
7.里親制度
補足資料
Discussion
12章 受精卵や胎児はいつから「ひと」になるのでしょうか
1.「ひと」はいつから「ひと」になるのか
- 1-1 生命の発生プロセス
- 1-2 母体側からの視点
2.「ひと」はいつから「ひと」でなくなるのか
- 2-1 生命の初期と終期の対称性
Discussion
13章 人の死─脳死と臓器移植─
1.心停止ともう1つの死
- 1-1 「脳死」の状態
2.臓器移植
- 2-1 臓器移植の歴史
3.脳死判定
- 3-1 一般の脳死判定
- 3-2 法的脳死判定
- 3-3 脳死判定の難しさ
4.日本の臓器移植法
- 4-1 日本初の心臓移植と臓器移植法の成立過程
- 4-2 臓器の移植に関する法律(1997年)
- 4-3 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(2009年)
5.脳死・臓器移植がもたらす問題
- 5-1 「脳死した者」の法的な位置づけ
- 5-2 家族承諾での臓器提供
- 5-3 15歳未満からの臓器提供
- 5-4 親族への優先提供
- 5-5 虐待された子どもからの臓器提供の禁止
6.救命治療と臓器保存
7.臓器移植にかかる費用
- 7-1 ドナーにかかる医療費
- 7-2 レシピエントにかかる医療費
8.生体臓器移植
9.臓器不足の意味を考える
10.臓器移植以外の治療
11.脳死は「人の死」かどうかについて考える
補足資料
Discussion
14章 人の死─安楽死と尊厳死─
1.安楽死と尊厳死の概念
- 1-1 安楽死という言葉が持つ意味
- 1-2 尊厳死という言葉が持つ意味
- 1-3 自己決定に基づいて分類される「安楽死」の種類
2.緩和ケア
3.ナチスの積極的安楽死政策―「慈悲による殺害」
4.日本における安楽死事件と安楽死が許容される条件
5.「消極的安楽死」から「尊厳死」へ
- 5-1 終末期医療における「治療中止」のあり方
- 5-2 消極的安楽死のガイドライン作成
- 5-3 カレン・アン・クインラン裁判
- 5-4 リヴィング・ウィル(事前指示書)の制度化
6.尊厳死法制化と臓器移植法の関係性
7.終末期医療の対策と変容
8.安楽死・尊厳死をめぐる問題点
- 8-1 安楽死・尊厳死を肯定する背景
- 8-2 事前指示書の存在と患者の意思
- 8-3 「無益」な延命治療
- 8-4 患者がどう生きたいか
9.死ぬ権利とは何か
10.「安楽に生きる」「尊厳を持って生きる」
補足資料
Discussion
まとめ
文献
索引