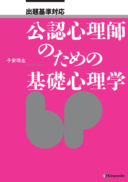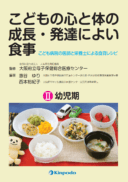医師・医療者が知っておきたい子ども虐待
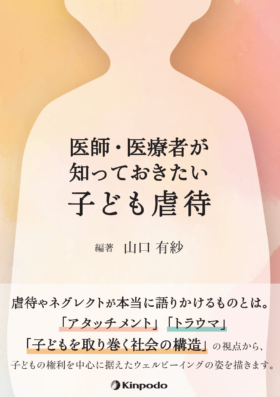
医学的視点 × 子どもの権利 × ウェルビーイングから捉えた、子どもの虐待の今
内容紹介
児童虐待の相談対応件数は年々増加し、医療従事者には虐待の早期発見と通告が義務付けられています。改訂された「医師臨床研修指導ガイドライン」でも、子ども虐待の研修が必須項目となりました。今、医療に関わるすべての人が子ども虐待について学び続け、知識をアップデートする必要性が高まっています。
本書では、子ども虐待を「子どもの権利とウェルビーイング」の視点から捉え直し、医療者としてどう向き合うことができるかを考えます。医療現場での虐待のサインをどのように察知し、適切にアセスメントし、ケアにつなげるか。さらに、「アタッチメント」「トラウマ」「発達」「社会の構造」といった多角的な視点から、子ども虐待を深く理解するための枠組みを提供します。
医師・医療者向けに、子ども虐待の理解と対応を深める一冊。子どもの権利とウェルビーイングの観点からも考察を深め、子どもとともにあるすべての医療者のための知識と視点を共有します。
序文
「助けてって言っても、変わらなかった。自分でなんとかするしかないって思った。」
児童相談所で出会った子どもの言葉です。その子は繰り返しの虐待の中で、学校や医療機関などで、不登校や心身の不調を訴えていました。けれども、その背景はなかなか気づかれないまま、いつしか自分のことを傷つけるようになり、繁華街を出入りするようになります。
「虐待を受けた子どもの診療をすることはほぼないのですが、知っておいた方がいいと思いまして。」
これは、私が虐待とネグレクトについての講演の依頼を受けた際に、医療者の方からいただいた言葉です。果たして、そうでしょうか。
子ども時代に、虐待やネグレクトなどの逆境的な体験のある人は、日本の統計でも3人に1人といわれています。医療機関で、ある人が10人の子どもに出会うとしたら、そのうちの数人は、何らかの傷つきの体験をしている子どもであるということです。さらに、その養育者の方も含めれば、その数はもっと増えます。私たちは、出会っているのです。「医療機関における子ども虐待とネグレクト」は必ずしも、身体的虐待の結果に外傷のある子どもの診療や、ネグレクトの結果として体重が標準よりも小さい子どもの診療だけを指すのではありません。子どもや養育者の方の声にならないサインや心身の不調、人間関係のしんどさの背景にある虐待やネグレクトに、私たちはきっと出会っています。心の中でちょっとした違和感を覚えていることもあるはずです。
本書には、主に医療者の方を対象として、子どもの虐待とネグレクトをどのようにとらえ、アセスメントし、ケアしたらいいか、ということをまとめました。特に、単に子どもの虐待とネグレクトに気づき、何らかの状態を診断し治療するという医学的なモデルを超えて、そもそも子どもの虐待やネグレクトが、子どもの権利とウェルビーイングの視点でどのような意味を持つのか、そして私たちのまなざしと振る舞いはどうあるべきか、ということに焦点を当てました。
記述の中には、虐待やネグレクトについての具体的な内容が書かれているものもあります。読んでいて、色々なことを考えたり思い出したりして、しんどくなることがあるかもしれません。それは皆さんにとってのとても大切なサインです。ぜひ、ご自身にとって無理のないペースで、時々休憩も取りながら、読み進めていただけたら幸いです。
本書をまとめた自分自身も、小児科の研修医のとき、当直で気になるご家庭に出会いましたが、何もできなかった苦い記憶があります。現在は、療育センターや児童相談所などで子どもに出会いながら、研究機関や国の機関にも関わっていますが、今でも、何の身動きも取れずに、無力感に打ちのめされることもあります。一人の母親として、わかっていてもできない葛藤を抱く中で専門家の言葉に傷つくこと、子どもに手を挙げそうになってトイレでクールダウンして戻ってきても目の前の状況が何も変わっていなくて絶望することも、たびたびあります。
私たちは誰しもが不完全な存在です。それでも、というかだからこそ、すべての人にとって、虐待やネグレクトが誰にでも起こり得ることだと知り、そのサインと対処方法を知っておくことで、すべての子どもたちの権利を保障するために力を合わせられると思うのです。
本書が今日の皆さんにとって、少しでも役に立つものであることを願っています。
子どもと養育者の方たちへの敬意と感謝とともに
2025年3月
山口有紗
目次
はじめに
第1章 子ども虐待・ネグレクトについて、今わかっていること・行われていること
1 ウェルビーイングを形づくるもの ~子どもの権利の視点から
- 1 子どもの権利の視点
- 2 エコロジカルモデルの視点
- 3 子どもの発達に不可欠な要素の視点
2 子ども虐待とは何か
3 どのくらいの子どもが影響を受けているのか
4 子どもの虐待とネグレクトに関わる政策
- 1 子どもの発達に不可欠な要素の視点
- 2 対症療法の充実
- 3 子どもの権利と予防的アプローチの萌ばえ
- 4 子どもの最善の利益と子どもの声
- 5 こども家庭庁とこども基本法
第2章 なぜ子ども虐待・ネグレクトに医療者が関わるのか
1 子ども虐待に関わる要因
2 アタッチメントと発達
3 子ども虐待のライフコースへの影響 ~子ども時代の逆境的体験と保護的体験に関わる研究
- 1 子ども虐待の短期的な影響
- 2 子ども時代の逆境的体験がライフコースを通しておよぼす影響
- 3 傷つきの中で育つこと
- 4 社会全体へ経済的な影響
- 5 リスクからレジリエンスへ~子ども時代のポジティブな体験
4 医療と子ども虐待・ネグレクト ~なぜ医療者が子ども虐待に関わるのか
- 1 虐待とネグレクトの予防
- 2 虐待とネグレクトへの気づきとケア
- 3 虐待とネグレクトを受けた後の中長期的なケア
第3章 子ども虐待の診断と治療
1 子ども虐待の診断
- 1 通常の診断との相違
- 2 虐待を疑う
- 3 子ども虐待・ネグレクトを疑ったときの診察
- 4 疑わしきは行動を起こす
- 5 子ども虐待を疑ったときの検査等
- 6 医学的診察や検査が重要な虐待
2 虐待を受けた子どもと家族の治療
- 1 身体医学的治療
- 2 治療中の養育者への説明と、養育者と子どもの接触
- 3 養育者と子どもの関係の治療
3 地域連携と社会的処方
- 1 虐待相談の後に起こること
- 2 要保護児童対策地域協議会
- 3 社会的養護のいま
- 4 一時保護所の子どもたち
- 5 社会的養護のもとにある子どもと医療
- 6 社会的な処方
第4章 トラウマインフォームド・ケア
1 トラウマインフォームド・ケアとは何か
- 1 ストレス反応について知る
- 2 トラウマインフォームド・ケア
- 3 トラウマとは
- 4 トラウマによって起こること
- 5 ケアする人のケア
2 メディカル・トラウマ
第5章 医療者にできること
1 エビデンスに基づいた柔軟な対応:子ども虐待対応の手引き
- 1 子ども虐待を疑う
- 2 子ども虐待に対応する
- 3 子ども虐待を予防する
2 院内虐待対応チーム(Child Protection Team;CPT)
- 1 院内虐待対応チーム(Child Protection Team;CPT)とは
- 2 MDT(Multidisciplinary Team)の重要性
- 3 CAC(Children’s Advocacy Center)とは
3 仲間を増やし、共に学ぶ
- 1 子ども虐待の卒前・卒後教育
- 2 医療機関向けの虐待対応啓発プログラムBEAMS(ビームス)
- 3 仲間を増やす
4 地域での保健師の役割
- 1 児童相談所で出会った子どもたち
- 2 保健師とは
- 3 妊娠期からの早期支援と長期的な視点を持った関わりの必要性
- 4 地域の保健部門の保健師の活動
- 5 児童相談所保健師の活動
- 6 医療機関と連携した事例
- 7 家庭の状況から見た各機関の役割
- 8 上流・下流の話
- 9 医療機関との連携
- 10 最後に
5 予防とケアのための一歩を踏み出す
- 1 虐待予防とは
- 2 子どもの育ちの基盤となる「安全で、安定した、あたたかい関係性と環境」とは
- 3 虐待予防のための親子関係性支援とは
- 4 虐待予防のための具体的支援策とは
- 5 まとめ
第6章 子どもの声からはじめる
1 子どもアドボカシーと医療
- 1 はじめに
- 2 子どものこえを聴くこと
- 3 すくい上げた声を社会につなげること
- 4 終わりに
2 子どもの声を聴く ~子どもアドボカシーとは何か
- 1 子どもの意見表明等支援とアドボカシー
- 2 子どもの声が聴かれない背景
- 3 独立/専門アドボカシーとは
- 4 「子ども抜きに子どものことを決めないで」を医療の世界にも
3 現場の声から
- 1 妊娠葛藤をつながる機会に
- 2 養育者のエンパワメント
- 3 言葉にならない「助けて」と共にあること
第7章 「病気の子どもの診断と治療」から「すべての子どもの尊厳とウェルビーイング」の医療へ
あとがき
執筆者一覧
■編著
山口有紗 子どもの虐待防止センター/国立成育医療研究センター
■執筆者一覧(五十音順)
栄留里美 西南学院大学人間科学部社会福祉学科
奥山眞紀子 子どもの虐待防止センター/山梨県立大学大学院人間福祉学研究科
希咲未來 顔出ししないActivist
小橋孝介 鴨川市立国保病院
田口美恵子 世田谷区児童相談所
田上幸治 神奈川県立こども医療センター総合診療科
辻由起子 こども家庭庁参与
中島かおり 特定非営利活動法人ピッコラーレ
松岡佳美 世田谷区烏山総合支所保健福祉センター健康づくり課
山岡祐衣 東京科学大学公衆衛生学分野
余谷暢之 国立成育医療研究センター総合診療部緩和ケア科