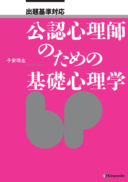感情がつくられるものだとしたら 世界はどうなるのか
-バレットの構成主義的情動理論をめぐる、さまざまな領域からの考察-

★2025年4月下旬 発売予定!★
「社会的に構成されている」という言葉が指す内容とは?
内容紹介
第122回日本内科学会総会・講演会(2025年4月18~20日・東京都)にて先行発売予定!
医学分野では、感情は生物学的な実体があるものとされてきました。その見解によって、例えばうつ病(不安障害)の薬物療法などが行われ、一方で同じうつ病でも社会的な影響によって生じているとされる部分は心理療法による治療が行われてきました。ただ、心理学者リサ・フェルドマン・バレットの主張するように、「感情とは根本的に社会的に構成されたものである」とすると、それは従来の見解をどのように変更したらいいのか、さらには実際の治療を変更しないといけないのか、という問いが生じます。これは精神科医に限らず、医療者全般、心理職の関心だけでなく、精神鑑定など社会制度にまで影響が及ぶ可能性があるでしょう。とはいえ、「社会的に構成されている」という言葉が指す内容は理解が難しいものです。そこで、哲学者・心理学者・神経学者によるバレット理論の解説を踏まえ、「感情が社会的に構成されている」という論に対する論説を並べました。
序文
本書のねらいは、感情(情動)に関する見方および実践について近年の認知科学・神経科学の知見を踏まえて考えるための着眼点や基本的な知識を、心理臨床や精神科臨床などの実践に関わる人々や、近年の科学的な心理学・神経科学の展開に関心をもつ読者に伝えることです。
私たち人間の心のあり方に関する見解には、人間の心である以上、そこには人類(ヒト)に普遍的な性質なり構造なりが備わっているという見方と、心が周囲の人々など環境との関わりのなかで展開してゆくものである以上、そこには個人や地域共同体に独特の性質なり構造なりがあるという見方があります。感情ないし情動のあり方に関していえば、個別的・環境的な要因、たとえばその地域独特の文化や風土といったものが影響を及ぼすという考えがあり、それはときに「細やかな四季の移ろいのない土地に育った西洋人に「もののあはれ」はわからない」などと、お互いの文化ないし民族の違いを際立たせるロジックとして、用いられてきました。しかしそれは、ある程度分化した複雑な感情にあてはまることであって、喜怒哀楽といった基本的な感情は文化や風土の違いを超えて人類一般に普遍的に備わるものであり、ヒトなど高等なサルないし哺乳類の「脳」にデフォルトとして生得的にインストールされたものである、という見方が一般的であるように思います。
たとえば、日本からアメリカ合衆国に渡ったコメディアンや野球選手の活躍に対する現地の人々の笑いや熱狂、あるいはオリンピックの舞台で表彰台を逃した海外の選手の悔し涙を、情動の表出として私たちは自然に理解します。基本的な感情のあり方と仕組みは文化や時代、さらにはもしかするとその一部は生物種の違いを超えて共通したものであり、21世紀の日本に生きる私たちの悲しみと古代ギリシアに生きた人々の悲しみ、さらに荒野を駆けるオオカミの抱く悲しみは、等しく「悲しみ」であり同様の身体(神経)的基盤によって成立する。およそ、このような前提のもとで私たちは生活しているといえるでしょう。
このような前提は、精神医学や臨床心理学の実践にもうかがわれます。たとえば臨床家は、過度の抑うつ(悲しみ)や不安(恐怖)がみられる患者さんに対して、DSMやICDなどの国際的な基準に基づいて「うつ病」や「不安症」といった診断を下し、治療においてはモデル動物によって効果を確かめながら開発された抗うつ薬や抗不安薬を用いるという実践を、とりたてて疑問を抱くことなく(あるいは漠然と疑念を抱いても立ち止まることなく)行っています。
感情(情動)に対するこのような私たちの暗黙の了解を学術的に裏付けるのが、情動には喜怒哀楽のような基本的かつ普遍的なカテゴリーがあるという見解です。基本的な情動は生物の脳にあらかじめインストールされており、ヒトはそうした情動を理性ないし認知の働きによって適切に制御しながら生きているというのです。感情(情動)についてのこの理論は、多くの実証研究によって支持されることによって、長い間、感情(情動)の理論の主流を占めてきました。
ところが、このような古典的情動理論に対して、最近、心理学者のリサ・フェルドマン・バレットは、それが情動についての本質主義であるとして非難し、古典的理論に代わりうる理論として「構成主義的情動理論」という見解を提唱しています(バレット『情動はこうしてつくられる』(Barret 2017=2019))。
バレットの見解は次のようなものです。(1)怒りや嫌悪といった基本的とされる情動のカテゴリーには本質は必ずしも存在しない。すなわち、古典的理論に従えば同じ情動カテゴリーに分類されることになるその都度の情動表出に共通する性質や、その共通の土台となる神経基盤は必ずしも存在しない。(2)人が経験・知覚する情動は、その情動概念が有意味かつ有用である特定の社会的文脈において、人が生きるなかで人の脳に組み込まれたものである。喜怒哀楽のような基本的な情動概念であってもその例外ではない。すなわち、基本情動を含む個別の情動は遺伝子(ひいてはヒトに共通する生物学的要因)によって確定されたものではない。(3)人は(脳は)外部からのあるいは内部からの様々な感覚入力に、脳に組み込まれた諸概念を用いることで、情動を構成(構築)し、情動として知覚・体験する。
こうしたバレットの見解は書籍発売後、TEDなどにも取り上げられ、その著『情動はこうしてつくられる』は英語圏で14万部売り上げ、13カ国で発売されるなど異例の売れ行きを見せました。バレットの構成主義的情動理論は世界的に関心を集めたといえるでしょう。それはおそらく、生得的かつ普遍的な情動の基本的カテゴリーという見方への批判がもつインパクトに加え、情動に関する近年の心理学や脳科学(認知神経科学)の展開を踏まえている、ということによるでしょう。しかし、バレットの著作や見解は、精神医学や臨床心理の臨床実践に携わる人々において、必ずしも知られてはいません。基本的な感情ないし情動として怒り、嫌悪、恐怖、喜び、悲しみ、驚きの6つがカウントされるという、バレットが批判の対象としている学説そのものが、精神科医にとっては基本見解として共有されたものではありません。その一方で、心は社会や文化の影響を受けながら形づくられてゆく(いわば「社会的に構成されてゆく」)といった見解は、手垢がついたと言いたくなるほど馴染みのあるものです。編者の一人(植野)はバレットの著作を一読したときに、どこが新しいのかがわからず、したがって、どうして世界的に関心を集めるのかの理由もわからず困惑しました。バレットの構成主義的情動理論や、その背景にある情動に関する近年の認知神経科学の知見は、情動に関する私たちの基本的見解について再考をうながし、さらには感情ないし情動をめぐる精神医学や臨床心理学の実践にも影響をあたえうるものです。それだけに、バレットのような専門的研究者と、一般の臨床家との知識や問題意識の乖離は残念なことです。
構成主義的情動理論や『情動はこうしてつくられる』などで展開された見解は、バレットのオリジナルなもので、近年の情動に関する認知神経科学の知見に基づいています。しかし、そこで扱われている論点にはそれぞれ長い議論の歴史があります。たとえば情動は生物学的に規定されるのか、それとも社会・文化的要因によって規定されるのかという問題、情動と理性との関係をどのように捉えるかという問題―欲求や情動を理性でコントロールするところに人間性を見出すという見解や、道徳的な価値づけのように人間の認知には情動に導かれる面もあるという見解―です。情動をめぐるこれらの古典的な論争について改めて考えるために、バレットの著作はうってつけの素材です。さらにその際、近年の情動に関する認知神経科学の展開について知識をアップデートする効果も期待できます。そのようなわけで、編者らは本書「感情がつくられるものだとしたら世界はどうなるのか」を企画しました。
本書では、主な読者層として、次の2つを想定しています。
(1)専門家(プロ):精神科医や心理士、看護師といった「こころ」の臨床実践に関わる専門家、そしてまた、感情(情動)に関する心理学・認知科学的な研究に携わっている専門家など、「感情」について取り組む専門家など。感情を扱うトレーニングや実践を積み重ねた専門家、あるいは感情について系統だった知識と実験的な取り扱いを学んだ専門家の方々に手に取っていただき、それぞれの専門的な実践の前提となっている見解や知見を再考するための基本的な知識を提供する。
(2)認知・神経科学の愛好家(アマチュア):認知科学・神経科学系のサイエンス・ノンフィクションを愛好する方々。こうした方々に向けて、バレットの構成主義的情動理論やそれが批判のターゲットとしている古典的な情動理論、また情動に関する科学および哲学的な知見と議論の文脈について信頼性のある情報を提供する。
本書は大きく分けて、第1部「感情概念は変貌する その科学と哲学」とそれに対する応答である第2部以降で構成されます。本書の前半である第1部では、構成主義的情動理論などの見解とその意義を理解するための基礎的な概念枠組み(感情と理性、社会的構成)や、心理学・神経科学的な知見・議論(基本的情動、いわゆる「三位一体脳」とそれに対する批判など)を、専門家に解説していただきます。本書の後半「応答編」では、バレットの構成主義的情動理論や、そこで参照されている感情(情動)の認知科学・神経科学の知見を手がかりに、「感情がつくられるものだとしたら世界はどうなるのか」という問いについて、感情・情動が関わる学問や実践領域の専門家に論じていただきます。
仮に、喜怒哀楽といった感情(情動)が、ヒトにとって生得的かつ普遍的なものではなく、文化や社会の影響のもとで構成されるものであると認めたならば、感情に関わる私たちの実践はどうなるのか、というのが本書の主題です。バレット自身、情動・感情に関する臨床的介入として情動概念を細やかにすることを推奨するなど、自らの理論の応用として臨床ないし実践上のレシピを提供しており、興味深いところです。また情動とそれをめぐる実践という主題は、倫理や司法の実践、心の哲学、感情の社会学、動物心理学といった分野にも関わる広い射程を備えており、それぞれが重要なものです。
「感情は社会の中でつくられる」ということを受け入れるとしたら、世界や社会に対する私たちの見方は変わるのだろうか。あるいは変わらないのだろうか。もし変わるとしたら、どのように変わるだろうか。そして、その変化によって、世界や社会に対する私たちの関与(コミットメント)はどのように変わるだろうか。このような問いについて考えるためのいくつかの着眼点、ならびに基本となるリテラシーを提供する。これが本書の目的です。
2025年2月
編集を代表して 植野仙経
目次
はじめに
第1部 感情概念は変貌する その科学と哲学
1 感情の哲学から見たバレットの感情理論
感情の哲学:歴史と現状
バレットの感情理論
バレットの感情理論:哲学的意義
2 心理学における感情の理論―構成主義理論による批判と基本感情理論による応答
はじめに
基本感情理論
構成主義理論
バレットから基本感情理論への批判
バレットの批判を検討する
おわりに
3 脳は感情と理性を対立させているか
はじめに
2つのこころ:感情と理性
心理構成主義
予測する脳とこころ
感情と理性の対立を止揚する
結論
4 感情は科学の概念なのだろうか
心理学・精神医学における概念使用の特異性
「自然種」をどのように特徴づけたらよいか
感情は自然種なのかという「論争」
「論争」の評価
ふたつの戦略を使い分ける
自然種なんて怖くない?
まとめ
第2部 心理学
1 発達科学の立場から―感情の成り立ちと教育
はじめに
発達科学における感情研究
感情語と感情概念の発達
感情の教育
おわりに
2 文化によってつくられる感情―文化心理学の立場から
畏敬感情の文化的構成
フロンティア仮説
ポジティブ感情の文化的価値
感情そのものの理解と文化
感情と健康
まとめ
3 シグナルとしての表情の進化―進化心理学の立場から
はじめに
「反射」としての表情 vs. シグナルとしての表情
シグナル説再考
おわりに
4 動物の感情研究とは何か? 霊長類の表情と感情ラベリング研究からの見解
バレットとダーウィン
emotionとfeeling
動物の「感情」研究は可能か
類人猿の表情研究―何が「相同」か?
表情認識の研究―顔はそんなに重要か
感情ラベリング―とにかく難しいラベリング研究
結論
第3部 精神医学・心理療法
1 バレット理論と精神医学
はじめに
バレット理論の概要
バレット理論からみた「心の病」
バレット理論が提起している問題
理由のあるデプレッションと理由のないデプレッション
おわりに
2 では非難される主体はどこにいるのか―司法精神医学の立場から
主体
理性
命令幻聴―二重過程理論による解釈
感情
命令幻聴―心理構成主義による理解
意思
3 心理構成主義的感情理論から見た心理療法―認知行動療法の立場から
認知行動療法における感情の扱い
心理構成主義的感情理論から認知行動療法へ
心理療法から心理構成主義的感情理論へ
4 感覚刺激から感情がつくられるまでに何が起こっているのだろうか―精神分析の立場から
はじめに
バレットの主張の要約
快・不快という例外的な感情
フロイトの最早期発達論における不快
フロイトの経済論とバレットの経済論
感情の構成プロセスにおける概念の役割
ビオンの転換とバレットの構成
ビオンの前-概念とバレットの概念
さいごに―どのような他者になるか
第4部 社会科学・工学
1 AI・ロボットに情動は創発するか―AI・ロボット研究の立場から
はじめに
認知発達ロボティクスの思想的背景の概略
身体性と感情・情動
直感的親行動による情動マッピングの獲得
社会的関係性に基づく共感発達
心的機能創発の要としての痛覚神経回路と人工痛覚
認知発達ロボティクスからの構成主義的情動理論考察
大規模言語モデルのインパクト
おわりに
2 心理構成主義は政治的行為を捉えなおせるか―政治学の視点から
「政治的なもの」とは
感情の地位
「政治科学」の登場
「合理性」とは?
政治学における感情論の再興
政治学における構成主義
感情は政治に欠かせない
3 相互行為の人類学による感情へのアプローチ―人類学の立場から
はじめに
間主観性の基盤としての感情
会話に用いられる感情語彙
まとめ
第5部 人文学
1 モラルにおける嫌悪の役割を考え直す―倫理学の立場から
序文
誰が嫌悪を感じるのか
暴露論証としての嫌悪懐疑論
感情の認識的な合理性:構成主義からの再編成
結論
2 動物の感情は倫理的に重要か―動物倫理の立場から
倫理学における価値論と福利論
価値論における感情の位置づけ
動物の感情についてのバレットの立場
限界事例からの議論と一人称説
構成された感情は価値を持つのか
3 感情論再考―キリスト教学の立場から
はじめに
バレットの感情理論
バレットの感情理論に学ぶ:キリスト教思想との交差点
古代キリスト教思想における感情
中世キリスト教思想における感情:トマス・アクィナスの感情論
おわりに
4 「こころ」と「感情」の概念とそのありかた―仏教哲学の立場から
イントロダクション
仏教とは
「こころ」とは
仏教哲学にもとづく「こころ」の位置づけ
仏教におけるこころの構造と機能
仏教における感情の位置づけ
基本感情理論と心理構成主義のいずれが是であるか
仏教倫理観にもとづく善きこころと感情のあり方
あとがき
索引
執筆者一覧
■編著者(五十音順)
植野仙経 京都大学医学部附属病院精神科神経科
佐藤弥 理化学研究所ガーディアンロボットプロジェクト心理プロセス研究チーム
鈴木貴之 東京大学大学院総合文化研究科
村井俊哉 京都大学大学院医学研究科精神医学
■執筆者一覧(五十音順)
浅田稔 大阪国際工科専門職大学/大阪大学先導的学際研究機構共生知能システム研究センター
伊勢田哲治 京都大学文学研究科
板倉昭二 立命館大学OIC総合研究機構
植野仙経 京都大学医学部附属病院精神科神経科
内田由紀子 京都大学人と社会の未来研究院
大坪庸介 東京大学大学院人文社会系研究科
大平英樹 名古屋大学大学院情報学研究科
太田陽 名古屋大学大学院情報学研究科
太田紘史 筑波大学人文社会系
狩野文浩 コンスタンツ大学・集団行動先端研究センター
国里愛彦 専修大学人間科学部
熊谷誠慈 京都大学人と社会の未来研究院
佐藤広大 筑波大学人文社会系
佐藤弥 理化学研究所ガーディアンロボットプロジェクト心理プロセス研究チーム
塩飽千丁 マランジェニー
鈴木貴之 東京大学大学院総合文化研究科
高田明 京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科
戸田山和久 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
中山真孝 京都大学人と社会の未来研究院
難波修史 広島大学大学院人間社会科学研究科
松村良祐 藤女子大学文学部
村松太郎 慶應義塾大学医学部精神・神経科
吉田徹 同志社大学政策学部